【中編】睡眠の質を上げる方法とは?生活習慣においてできる工夫や効果的な運動などを解説!

読者の皆さんの中には、睡眠の質を上げるために寝ようとしても、頭が冴えてしまって、なかなか寝付けないという方もいるのではないでしょうか。しかし、日ごろの生活における工夫や、適度な運動をおこなえば、睡眠の質を上げることができます。
前回の記事では、睡眠の現状やメカニズム、睡眠不足の原因、デメリットなどについてお伝えしました。
中編では、年齢別の最適な睡眠時間や、どうしたら睡眠の質を高められるのか、生活習慣での工夫や日中にできる運動の観点から、理学療法士の小島さんと内藤さんにお話を伺います。
年齢別の最適な睡眠時間は?
最適な睡眠時間について、年齢別でご説明いたします。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、それぞれ、以下の睡眠時間を取ることが推奨されています。
- 1~2歳:11~14時間
- 3~5歳:10~13時間
- 小学生:9~12時間
- 中学、高校生:8~10時間
- 成人:6~8時間
高齢者においても一般的には6~8時間が推奨されますが、睡眠不足よりも8時間以上睡眠を取る、もしくは布団に入っていると健康面のリスクに影響があります。そのため、高齢者は、布団に入ってからの時間が長くなりすぎないようにする必要があります。
また、推奨される睡眠時間が取れていなくても睡眠休養感(睡眠で休養が取れているという感覚)があると、健康面のリスク軽減につながります。年齢別に推奨されている睡眠時間を確保しつつ、睡眠休養感や日中の眠気の程度を考慮しながら、自身にとって最適な睡眠時間を見つけることが大切だと考えられます。
必要な睡眠時間は季節で変わる?
睡眠サイクルは、日照時間の影響も受けるため、日の長い春から夏は、日の短い秋から冬よりも睡眠時間が短くなりやすいとされています。また、特に夏は、日照時間に加えて、高温・多湿となり、入眠困難感(寝つきにくさのこと)や中途覚醒(睡眠の途中で目覚めてしまうこと)が増えやすくなります。
一方で、冬は気温が低く、日の出の時間が遅いことから、入眠困難感や起床困難感(寝起きが良くないこと)が増えやすくなります。これらのことから、季節に合わせて、エアコンを使用したり、カーテンを活用したり、寝室環境を整えることが睡眠の質向上につながると考えられます。
必要な睡眠時間は個人差がある?
必要な睡眠時間には個人差があることが報告されており、6時間未満の睡眠でも充足するショートスリーパーと10時間以上の睡眠を必要とするロングスリーパーの方が一定数存在します。このような方は、一般的に推奨されている睡眠時間に合わせると、かえって睡眠不足や睡眠の質を下げてしまう可能性があります。
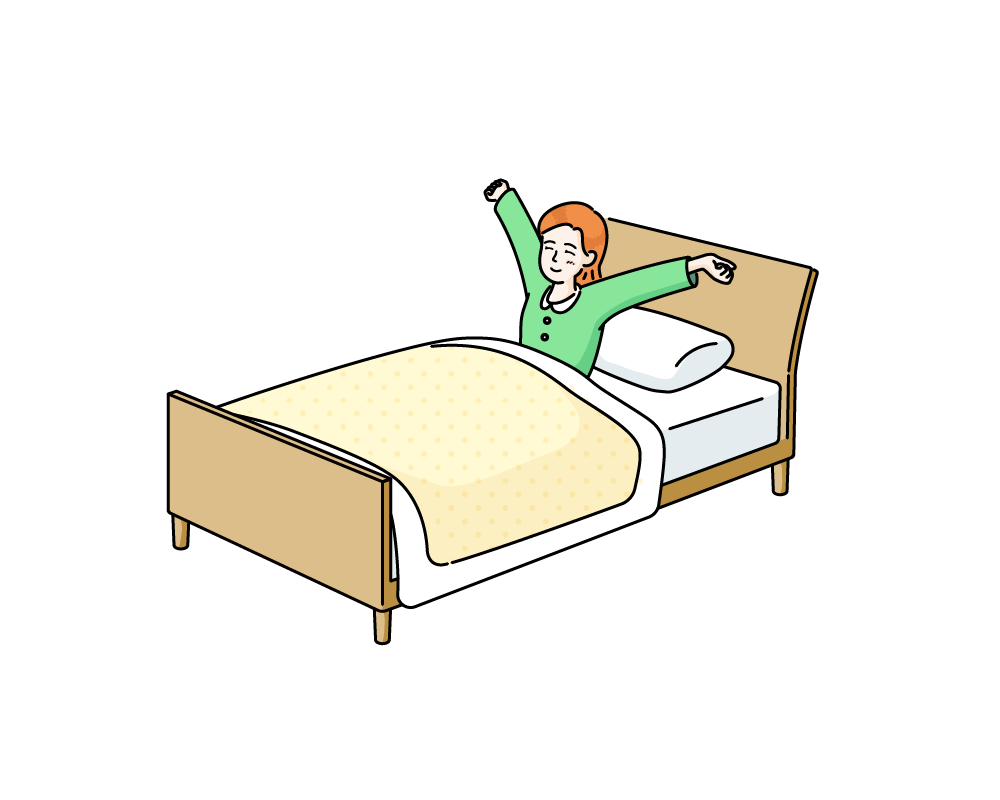
睡眠によるメリットとは?
・子どもにとってのメリット
乳児期から青年期にかけては、心身の発達・発育において最適な睡眠時間を確保することが重要です。睡眠を取ると、肥満や気分障害の予防にもつながります。
また、睡眠が充足すると、学習や技能の習熟が得られやすくなることから、学業や部活動の成績の向上につながる可能性があります。子どもは発達段階に伴って睡眠リズムが変化し、親の睡眠習慣の影響を受けやすいため、発達に合わせて最適な睡眠が取れるよう、親としてサポートが必要です。
・成人にとってのメリット
最適な睡眠時間を確保することは将来の疾患発症リスク(※)を最低限に抑え、健康寿命の延伸につながると考えられます。また、睡眠時間を確保できていると、集中力を求められるような作業に、より効率的に取り組むことができます。
※疾患発症リスクについては前編をご覧ください。



