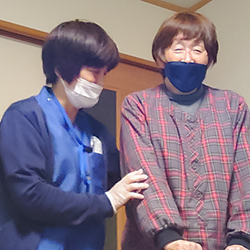ご自身の子育て体験を交えながら、親子で運動を楽しむことが大切と話す佐藤さん
ご自身の子育て体験を交えながら、親子で運動を楽しむことが大切と話す佐藤さん 【後編】佐藤弘道さんインタビュー 脊髄梗塞の後遺症と向き合う体操のお兄さん~「運動嫌い」の人はいない。家族と一緒に運動習慣を身に付ける方法とは~

身体を動かす楽しさと、“自分で身を守れる“身体の使い方を伝えよう
子どもの頃からの運動習慣は非常に大切だと感じました。しかし、運動をする子どもとしない子どもの二極化が進み、身体機能の発達が気になる子どもが多くなっているのが現状です。子どもに運動習慣を身に付けてもらうにはどうしたらよいか、そして私たち大人は、忙しい中で子どもとどう関われば良いか、教えていただけますか?
佐藤さん:子どもに運動が楽しいことをわかってもらうには、子どもと一番近くにいる親が一緒に動くことが大事です。
自分の体験からお話ししますが、子どもとの付き合いは「量より質」だと思っています。我が家には二人の息子がいますが、子どもたちが小さいころ、体操のお兄さんとして忙しくて、なかなか一緒に遊ぶ時間がとれませんでした。なので、時間があるときは全力で一緒に遊ぶようにしていました。
近くのグラウンドで一緒にトラックを走った時は、わざと息子たちと反対周りで走っていました。するとランニング中にお互いが何回か出会うので、同じ方向を向いて一緒に走るより、コミュニケーションの回数が多くなります。
今は仕事で忙しくてお子さんと一緒に過ごす時間がとりづらい方も増えていると思います。お子さんが小さければ、保育園などにお迎えに行くときはスマホを置いて、子どもの手をしっかり握ってあげてください。
親から愛されている子どもは、自分が大人になったときも、自分の子どもを愛してあげられると僕は思っているんです。親の愛情の積み重ねが、子どもたちの先の代まで繋がっていきます。だから、子どもには精一杯の愛情を注いであげてほしいです。
最近の子育てでは、親が危険回避を優先して、子どもが危険な目にあわないように先回りすることが増えていると思います。子どもの成長には、少しの冒険も必要なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
佐藤さん:今の保護者たちは危険回避を優先しますが、子どもは少しくらいやんちゃで良いと思います。そのほうが、遊びを通して自分を守る動きや身体の使い方を覚えられると思うんです。だからといって放任するのではありません。木登りをさせるときは、好きなように登らせるけれど、安全に下りる方法は教えてあげるようにします。
最近、体操教室が増えてきていますよね。教室に通うのもいいと思いますが、体操教室に行かなければ運動能力を高められないということはありません。「子どもの体幹を鍛えたい」という方には、体幹トレーニングを受けさせなくても、遊びながら鍛えることができるんです。
先ほど述べたように、僕の脊髄梗塞からの回復には、子どものころから身体を動かすことが好きで、いろんな動かし方を知っていることが役立っていると思います。どうかお子さんには汚れてもいい服を着せて、外遊びを楽しませてあげてください。
思いっきり遊び、思いっきり動くことで、身体を動かすことの楽しさを知り、自分の身を自分で守る動きを身に付けることができます。さらに、運動の楽しさや気持ちよさを知っていると、大人になってからも運動習慣を保ちやすいのではないかと思います。